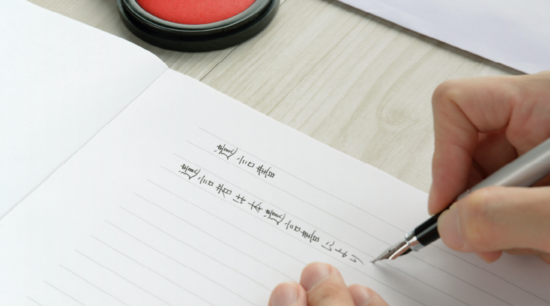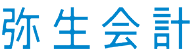新着情報
戦う税理士 小栗のメールマガジン
「相続対策で自宅を信託財産にしても小規模宅地の特例は受けられます」No.991
皆さん、こんにちは!戦う税理士の小栗です。
すでにインフルエンザが流行ってきているようです。早めの予防接種が必要ですね。
冬の季節は繁忙期になりますので、当事務所も希望者は全員が早めの予防接種に備えています。
さて、自社株対策に「議決権分離型信託契約」という信託方式を使うことについては、
このメルマガでも何度かお伝えをしていますが、
いわゆる民事信託を使って不動産の相続対策をすることもよく使われる手法です。
特に高齢になった親御さんの自宅などを
信託で子供の名義にするなどは巷でもかなり普及してきています。
ということで今回の
「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは、
「相続対策で自宅を信託財産にしても小規模宅地の特例は受けられます」です。
信託というのは、委託者:不動産を預ける人、受託者:不動産を管理運用する人、
受益者:不動産からの利益を得る人、このような関係になり信託契約を結ぶと、
その不動産は信託受益権という権利に変わり、名義も受託者の名義に変わります。
どのような場面が考えられるかというと、
父親が高齢になり自宅の管理もままならなくなってくると、
いざという時に売却をしたくても認知症にでもなっているとそれもできなくなってしまいます。
そのような時に、子供が受託者となり自宅を管理するのです。
これで名義は子供に変わりますので、契約の内容次第ですが
自宅の改修や売却も子供ができるようになります。
名義は変わりますが、実質的な所有者は父親のままですので贈与税などはかかりません。
では、父親に相続が起こった時にはどうなるのでしょうか。
子供は信託受益権を相続して自宅を相続したと同じ事になります。
この時には信託受益権は相続税の対象となります。
ここで問題が発生します。
通常、自宅の相続があった場合には「小規模宅地の特例」といって、
一定の条件を満たしていればその評価を80%減額してくれるという制度があり、
これが使えるかどうかで相続税の額も相当変わってきます。
問題なのは、自宅ではなく信託受益権を相続した場合でも
「小規模宅地の特例」が使えるのかという点です。
実務家の間でも混乱があるところなのですが、
特例の要件を満たしていれば問題なく特例を使うことができますのでご安心ください(措通69の4-2)
不動産が別の権利に変わってしまっているので分かりにくいのですが、
実質的な所有者の変更は相続で行われているので問題はないという解釈です。
色々な財産を信託していて、相続と共に終了するような信託契約の場合で、
残余財産の中に自宅が含まれる場合でも「小規模宅地の特例」は使えます。
このように、最近の相続では相続税だけではなく、
民法や信託法まで考えて対策をしなければならないので少し難しくなってしまいました。
逆にそれらの法律を駆使することで、より的確な対策が打てるようになっているとも言えます。
STRグループでは、司法書士法人STRで民事信託、議決権分離型信託などの
コンサルティングも行っていますので、気になった方はぜひご相談ください。
では、次回もお楽しみに。
↓前回のメルマガはこちら↓