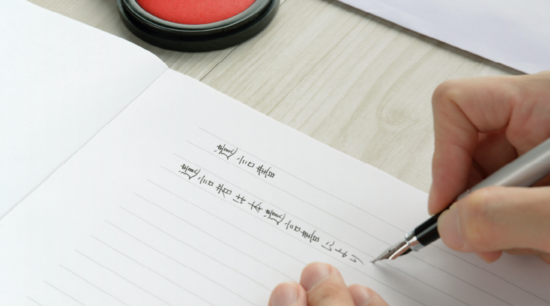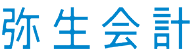新着情報
戦う税理士 小栗のメールマガジン
「組織再編税制(合併)を行う際の注意点を整理してみました」No.989
皆さん、こんにちは!戦う税理士の小栗です。
最近はホールディング会社を設立するなど、
中小企業でもグループ経営を意識した経営体制を作るケースが増えています。
STRでも数多くのお手伝いをさせていただいておりますが、
不採算の会社を合併させたり、新しい会社を会社分割で設立したりと
グループ内で組織再編を行うことが多いと思います。
ということで今回の
「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは、
「組織再編税制(合併)を行う際の注意点を整理してみました」です。
一般的にこのような企業の合併や会社分割などが行われる時に
適用される税法を「組織再編税制」といいますが、
要件を満たしていれば(適格要件)非課税で問題なく実行できることになっています。
この組織再編税制ですが、
「組織再編成の行為計算否認規定( 法法132の2 )」というのがあり、
適法であれば何でも認められるということではなく
租税回避の目的がある場合には否認がされるという仕組みになっています。
租税回避という言葉がとてもあいまいで、
我々実務家も頭を悩ませるケースも少なくありません。
今回取り上げるのは、現在係争中のゴルフ場運営会社のケースです。
P社の子会社としてA社、B社、X社があり
A社が多額の欠損金を抱えておりました。
A社とB社の合併してからX社と合併させるという行為により、
A社が抱えていた多額の欠損金をX社に引き継がせたということが論点となっております。
国税側は、不自然な合併であり租税回避目的が顕著だとして否認をしていましたが
地裁、高裁ともに合理的な理由があるとして納税者が勝訴しています。
どうも、最高裁まで争うようなのです。
論点になっている主な部分は下記のとおりです。
(1) 当該法人の行為又は計算が、通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり、
実態とは乖離した形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどうか
(2) 税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの
合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか
これは、節税以外の目的があるということをきちんと説明(経済的合理性)できないといけないですよと、
常々言っているところなのですが、今回もやはりそこが問題となっています。
細かい話は省きますが、判例でも明らかになっているのは
欠損金を引き継いで節税をしようとしたことについては裁判官も否定をしておりません。
それよりも、合併をする必要があったのかという経営的な判断をしています。
ここはとても重要で、
合併をさせずに赤字の会社を清算して消滅させることもできたはずなのに、
それをしなかったことは不自然だという国税側の主張に対して、
必ずしも不自然とは言えないという判断を下しています。
詳細までは分かりませんが、グループ全体として最小の課税となるように検討をして
資金を効率化させることは経営上の判断としては正しいはずです。
会社を残して合併させることがグループ全体として必要であったことを
取締役会議事録や事業計画書で説明ができるようにしておくなど
いざという時のための準備を怠らないことが重要だということですね。
組織再編など普段でてこない難問に困られたら、
ぜひ相談をしてみてください。
では、次回もお楽しみに。
↓前回のメルマガはこちら↓